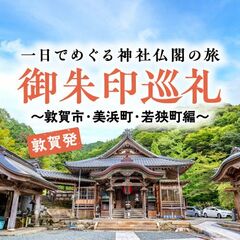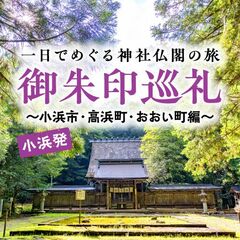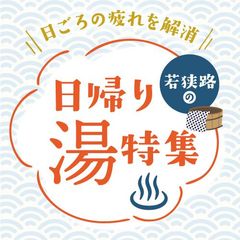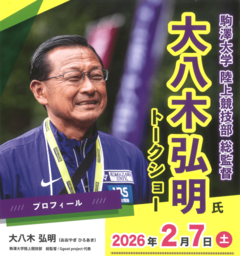水月湖から今年6月に採取されたばかりの年縞と掘削の成果を説明する長屋憲慶学芸員=若狭町の県年縞博物館
水月湖から今年6月に採取されたばかりの年縞と掘削の成果を説明する長屋憲慶学芸員=若狭町の県年縞博物館 採取した年縞を取り出す装置などが展示されている会場=若狭町若狭三方縄文博物館
採取した年縞を取り出す装置などが展示されている会場=若狭町若狭三方縄文博物館
福井県若狭町の水月湖で11年ぶりに行われた年縞(ねんこう)掘削を記念し10月8日、特別展「水月年縞2025」が同町の県年縞博物館などで始まった。立命館大などのチームは8月までの3カ月で湖底から70メートル分を掘削しており、会場には170年分となる約40センチの年縞を展示した。気候が慢性的に不安定化する「暴れる気候」解明への“手がかり”が見られる貴重な機会となっている。
年縞は1年に1枚ずつ堆積する特殊な地層で、含まれる花粉や元素組成を調べることで当時の気候が分かる。掘削は立命館大など国内外の研究機関によるプロジェクトチームの研究の一環で行われ、同大の中川毅教授らが取り組んだ。特別展は年縞博物館と町若狭三方縄文博物館が主催した。
展示されているのは今年6月に湖底から取り出し、アクリル製パイプで保管した年縞。常設展の年縞は、縞模様のある断面を展示しているが、今回は手が加えられていない“生”の状態で、表面は黒っぽい色をしている。上からのぞくと、今年の夏に藻が腐り黒くなった層がたい積しているのが確認できる。
湖底約70メートル分の堆積物の断面を撮影した写真を1~2メートルずつ印刷した紙も並べた。1993年の第1次調査では湖底45メートル、7万年分の年縞が連続していることが初めて確認された。今回も湖底45メートル以上は年縞があったが、それより深い場所では、年縞がないことなどが分かる。このほか、台船での掘削の様子など11年ぶりの年縞調査を記録した写真75枚も並ぶ。
縄文博物館では、水月湖畔に設置された仮設研究棟を再現。長さ2メートルのステンレス製のパイプから年縞を取り出す装置も展示した。中川教授が発案したもので、採取した年縞をワイヤを使って縦半分に切断する過程を作業現場の写真も交えて紹介した。
酸化による年縞の変色や退色を防ぐため二酸化炭素ガスで満たした木箱に入れて撮影する工夫なども展示物で説明。年縞を長期保存するために台所で使う食品ラップを使ったり、年縞の保湿のために生花用のスポンジを利用したりするアイデアも紹介した。
年縞博物館の長屋憲慶学芸員は「常設展示にはない、貴重な生の年縞や研究現場のリアルな姿が分かる展示をぜひ楽しんでほしい」と来場を呼びかけている。
両館とも来年1月12日まで。火曜休館。入館料は一般500円、小中高生200円。共通入館券は一般700円、小中高生280円。
(※福井新聞社提供。無断転載を禁止します。記事に関するお問い合わせは福井新聞社へ。)