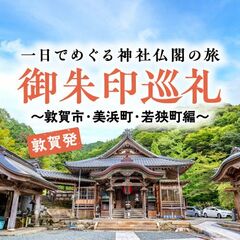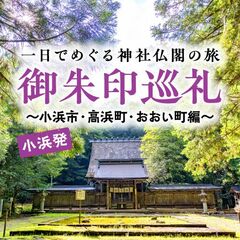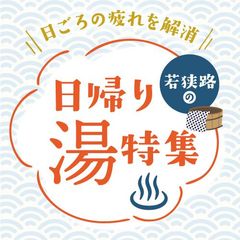松原神社例大祭・161年間続く敦賀の人々の想い

皆さん、初めまして。2025年10月1日より福井県庁地域おこし協力隊「敦賀・若狭エリア魅力発信ライター」に就任しました山田です。これを機にサラリーマン生活に別れを告げ、東京から福井県小浜市に移住してきました。これから福井県嶺南地域(敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町)の魅力を発信していきますので、よろしくお願いします。
今回の取材は、港都つるが観光協会から情報をいただきました。敦賀市にある松原神社で10月10日例大祭が執り行われるとのこと。着任早々、取材のネタをいただけて、感謝いたします。

松原神社は日本三大松原のひとつ気比の松原の近くに位置しています。敦賀駅から移動すると、タクシーで7分程度。敦賀市コミュニティバスの松原線や常宮線、ぐるっと敦賀周遊バスも利用できますが、あらかじめ運行時間を確認し、スケジュールを立てておくことをお勧めします。
幕末にあたる1864年、水戸藩の急進的攘夷論者たちが筑波山で挙兵し、幕府軍と衝突します。彼らは水戸天狗党と称し、武田耕雲斎を首領として約1千人が京に向かいました。京にいる一橋慶喜を頼りに、朝廷に尊王攘夷の志を訴えることが目的でした。
一行は中山道から美濃路を西に進みますが、幕府側の彦根藩が行く手を阻みます。衝突を避け、天狗党は北に進路を変更しました。隊列は降雪のなか越前に入り、敦賀・新保まで移動するも加賀藩を中心とした諸藩の大軍勢と遭遇します。皮肉にも、幕府軍の総大将は、一橋慶喜でした。
尊王攘夷の志は慶喜には届かず、天狗党は降伏しました。幕府軍は天狗党を罪人として扱い、北前船で運ばれてくる肥料のニシンを貯蔵する「鯡蔵(にしんぐら)」に幽閉しました。その環境は劣悪で、寒さや栄養不足などが原因で命を落とす者もいたとのことです。
結果として、天狗党は首領である武田耕雲斎をはじめ353人が処刑され、彼らの故郷から遠く離れた地で非業の死を遂げます。敦賀の人々は浪士たちを気の毒に思い、寺では法要が営まれるなど、供養を続けました。明治になると武田耕雲斎等の墓碑近くに松原神社を造営し、戦死者や病死者も含めた411柱を神として祭ったのです。
1964(昭和39)年、松原神社100年祭がきっかけとなって、翌年には敦賀市と水戸市とで姉妹都市提携が結ばれ、現在では天狗党の人々の故郷である常陸太田市、潮来市とも交流が続いています。例大祭は毎年10月10日に行われ、今年で161回を迎えました。

神社境内には見事な松が生い茂り、静謐な雰囲気に包まれています。住宅街にも隣接していますので、時折り保育園児などの笑い声も聞こえてきました。静けさとのどかさが入り混じるなか、例大祭は厳かに営まれました。各市長をはじめ、ご遺族の方々など多くの方が参列されていました。


松原神社から道を挟んだ場所に、武田耕雲斎等墓地があります。武田耕雲斎の銅像は気高さを誇り、墓地は開放的できれいに整備されていました。天狗党の凄絶なる運命と、それを脈々と弔ってきた地域の人々の想いを想像すると、もっと歴史を知りたくなります。小説の題材としても価値がありそうですが、幸いにも私が好きな作家・吉村昭氏が「天狗争乱」という作品を執筆していました。熟読して当時の様子を知り、理解を深めたいと思います。
(取材日:2025年10月10日)
福井県地域おこし協力隊
敦賀・若狭エリア魅力発信ライター 山田慎一
インスタでも発信しています!
ぜひご覧ください♪
⇒Instagramアカウント:https://www.instagram.com/tsurugawakasa_writer