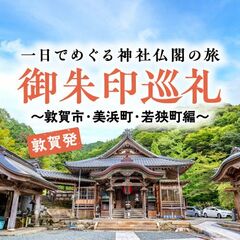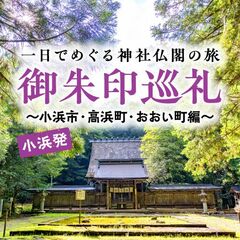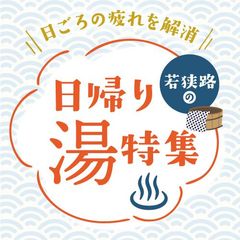集落の家々に伝わる化粧まわしを着けて披露された相撲甚句=14日、敦賀市阿曽の利椋八幡神社
集落の家々に伝わる化粧まわしを着けて披露された相撲甚句=14日、敦賀市阿曽の利椋八幡神社 勇壮に奉納された赤崎獅子舞=14日、敦賀市赤崎の八幡神社
勇壮に奉納された赤崎獅子舞=14日、敦賀市赤崎の八幡神社
集落の家々に伝わる化粧まわしを着けて披露された相撲甚句=14日、敦賀市阿曽の利椋八幡神社
福井県敦賀市東浦地区で9月14日、県無形民俗文化財に指定されている阿曽の「阿曽相撲甚句」と赤崎の「赤崎獅子舞」がそれぞれの区内の神社で奉納された。地域住民らが秋の実りへの感謝や悪霊退散、家内安全の願いを踊りに込めた。多くの見物客を魅了した。
同市阿曽で約350年続くとされる相撲甚句は、区内の利椋(とくら)八幡神社で行われた。まず区内外の子どもや大人が奉納相撲を見せ、観衆を沸かせた。
相撲甚句は、集落の家々に代々伝わる赤や青、黒の豪華な化粧まわしを着けて、区民ら10人が土俵入り。「そろうたョ~、そろいましたがョ~」と甚句の謡いが始まると、「ヤストコ、ヤストコ、ヤストコ、ショイ」のかけ声とともに、手拍子を入れながら土俵内を回った。テンポの穏やかな大踊りと少し速い小踊りを繰り広げた。
江戸時代からの歴史がある赤崎獅子舞は、同市赤崎の八幡神社で行われた。地元の奉賛会の会員ら18人が、六つの演目を披露し、五穀豊穣(ごこくほうじょう)などを祈った。
獅子頭をかぶった「踊り子」と、おかめの面を付けた「尾持ち」の2人による「鈴の舞」で幕開け。ゆったりとしたテンポの笛と太鼓の音色に合わせ、息の合った舞を見せた。猿やてんぐなどにふんした会員が、ささらをこすったり鐘を鳴らしたりして獅子の眠りを妨げる「寝の舞」なども、独特な舞で演じた。
担い手不足を理由に参加した、いとこ同士の高校生2人は「会員の人にアドバイスをもらい、練習の成果が出せた」と汗をぬぐった。
(※福井新聞社提供。無断転載を禁止します。記事に関するお問い合わせは福井新聞社へ。)