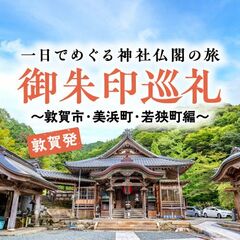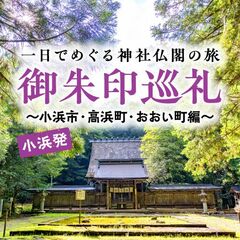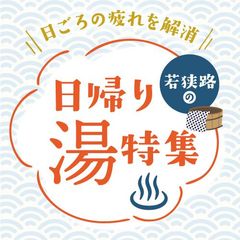敦賀まつり最終日の「新内演奏会」と「新内流しの夕べ」をPRするポスター
江戸時代に生まれた浄瑠璃の一派で、福井県敦賀市ゆかりの新内節(しんないぶし)の人間国宝、鶴賀若狭掾(つるがわかさのじょう)さんらによる「新内流しの夕べ」は9月4日、同市神楽町1丁目商店街で開かれる。当日は敦賀まつり最終日で、街中の別会場では市民による民謡踊りの夕べも繰り広げられる。哀愁を帯びた三味線に乗せた新内流しとの対比が楽しめる。
新内節創始者の初代鶴賀若狭掾は江戸時代、敦賀の紙屋町(現元町)で両替商を営んでいた若狭屋に生まれたとされる。花街を舞台に女性の悲しい人生を語る名曲を次々と発表した。舞台で行われていた浄瑠璃を歩きながら弾き語る「新内流し」と呼ばれるスタイルで、江戸で一世を風靡(ふうび)した。
現在の家元は2000年に11代目を襲名し、翌年、人間国宝に認定された。敦賀にはこれまで公演などで訪れており、敦賀まつりで街中で流しを披露するのは2009年以来となる。
4日は鶴賀若狭掾さんや鶴賀伊勢吉さん、鶴賀鶴二郎さんら8人が出演。午後3時半から敦賀北公民館で「新内演奏会」が開かれる。演目は、新内流しと蘭蝶、新内十三夜。古今亭志ん丸さんによる江戸落語もある。
「新内流しの夕べ」は午後6時半からで、出演者は神楽町1丁目の商店街で三味線を弾きながら着流しで街角を巡行する。途中に舞台を設け鶴賀若狭掾さんの語りが披露される。
演奏会、流しの夕べとも観覧は無料で、市民有志でつくる「新内節をきく会」が主催する。事務局長の梶野紀和さんは「新内節は敦賀がルーツ。市民の誇りである山車(やま)の巡行や民謡踊りの日に披露できることを喜びたい。敦賀にゆかりのある江戸の粋を楽しんでほしい」と話している。
問い合わせは梶野さん=電話0770(22)1709。
(※福井新聞社提供。無断転載を禁止します。記事に関するお問い合わせは福井新聞社へ。)