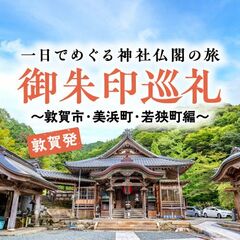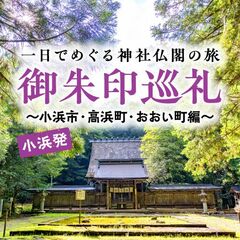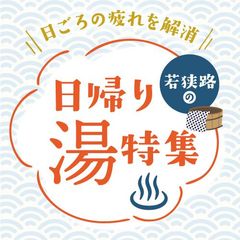(左)敦賀市文化財に指定された敦賀まつりの山車巡行(上)宵山行事で踊りを奉納する子ども
(左)敦賀市文化財に指定された敦賀まつりの山車巡行(上)宵山行事で踊りを奉納する子ども (左)敦賀市文化財に指定された敦賀まつりの山車巡行(上)宵山行事で踊りを奉納する子ども
(左)敦賀市文化財に指定された敦賀まつりの山車巡行(上)宵山行事で踊りを奉納する子ども
(左)敦賀市文化財に指定された敦賀まつりの山車巡行(上)宵山行事で踊りを奉納する子ども
敦賀市は8月29日、気比神宮の例大祭に合わせた敦賀まつりの山車(やま)巡行と前夜祭に位置付けられる宵山行事を市の無形民俗文化財に指定した。敦賀湊の町衆文化を伝える行事として価値が高いとしている。市文化財は147件となり、うち無形民俗文化財は5件目。
市の文化財調査報告書によると、山車巡行の起源は室町時代後期にさかのぼる。旧暦8月3日から4日にかけ、御所辻子(ごしょのずし)(現元町)の天満神社がかつてあった場所への神輿(みこし)渡御に付き従う町衆の祭りとして始まったとみられる。江戸時代には12の町が東西に分かれ隔年で6基ずつ曳(ひ)き出す「大山車」が巡行したという。
1945年の敦賀空襲で山車の多くが消失し、巡行は一時途絶えたが、70年に金ケ辻子(かねがずし)山車が市に寄付されたのを機に復活の機運が高まった。78年に御所辻子山車の巡行が再開すると、79年にはつるがの山車保存会が結成され、現在まで6基の巡行が保存会によって続けられている。
一方、宵山行事は宵山と呼ばれる山車が巡行する。2層式で屋根を持つ宵山の舞台では、日本舞踊やお囃子(はやし)の太鼓が演じられる。お囃子は、長唄の曲から採られた「二上がり」など6曲から成り、巡行時に順番に演奏される。現在は神楽町1丁目宵宮山車委員会が行事の管理者となっている。
今年の敦賀まつりは9月2~4日の日程で、宵山は2日、山車巡行は4日に行われる。
(※福井新聞社提供。無断転載を禁止します。記事に関するお問い合わせは福井新聞社へ。)