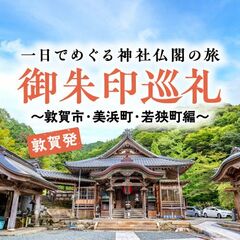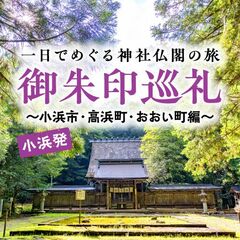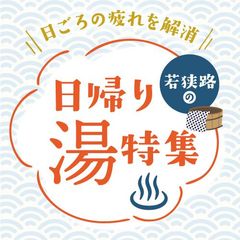仏壇の前で鉦の音、念仏に合わせ舞を奉納する児童=13日夜、小浜市西相生
福井県小浜市西相生の奥窪谷集落で8月13日夜、若狭地方の伝統行事「六斎念仏」が営まれた。子どもや大人たちが全23戸の仏壇前で、にぎやかな鉦(かね)の音や念仏に合わせて舞や太鼓を奉納、先祖の霊を迎え供養した。
「奥窪谷の六斎念仏」は江戸時代中期から続けられ300年以上の歴史があるとされる。舞は小学生の「一六斎(ひとろくさい)」、中学生の「二六斎(ふたろくさい)」、大人の「三六斎(みろくさい)」の3種類があり、各家庭の仏壇前で3人一組で演じる。地元有志でつくる保存会が引き継いでおり、現在では、8月13日の御霊巡回のほか、1月の仏法始めや9月の秋祭り、11月の鉦納めで奉納している。2004年、県の無形民俗文化財に指定された。
午後6時半ごろ、黄色い和服「カンバン」を着た小学生から大人まで30人が集落内の隣慶院に集合。二手に分かれて集落全戸をはじめ、観音堂や墓地などを約3時間かけて巡った。
大人衆が「カンカンカカカン」と鉦をにぎやかに打ち鳴らし念仏を唱える中、児童は7月から励んできた稽古の成果を披露。片手に持った太鼓を振り回すように左右に持ち替えたり体を入れ替えたりして舞った。
「目立つよう動作を大きくしたい」「みんなにほめられるよう頑張る」と話していた口名田小の児童らは汗だくになって奉納、訪問先の住人から拍手が送られていた。
(※福井新聞社提供。無断転載を禁止します。記事に関するお問い合わせは福井新聞社へ。)