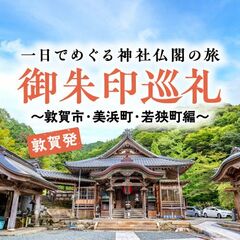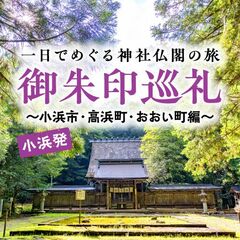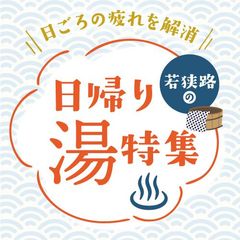区民らに引かれて6年ぶりに区内を巡行する重厚なみこし=26日、美浜町早瀬
区民らに引かれて6年ぶりに区内を巡行する重厚なみこし=26日、美浜町早瀬 日吉神社でクレーンを使ってつり上げられるみこし=26日、美浜町早瀬
日吉神社でクレーンを使ってつり上げられるみこし=26日、美浜町早瀬 区民が集まる中、慎重にクレーンで降ろされるみこし
区民が集まる中、慎重にクレーンで降ろされるみこし
福井県美浜町早瀬の伝統行事「水無月(みなづき)祭礼」が7月26日、始まった。江戸時代に北前船主から寄進されたと伝わる重厚なみこしを、山ぎわにある神社からクレーンを使って平地まで降ろし、特注の金属製の台車に載せて、6年ぶりに区内を巡行した。コロナ禍や高齢化で搬出できなかったみこしの再登場に、祭りは盛り上がりをみせた。
祭礼はもともと「河濯祭(かわそまつり)」と呼ばれ、三方五湖の水が日本海に注ぐ早瀬川河口で罪やけがれを洗い流すおはらいの儀式が起源。水の恵みに感謝する行事として受け継がれている。
美浜町は昨年、日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間~北前船寄港地・船主集落~」の認定自治体に追加。みこしはその構成文化財の一つとなった。地元では1・3トンの重さがあると伝わっている。
水無月祭礼は2020年からコロナ禍で中止となり、さらに祭礼が復活した23年と翌24年もみこしの担ぎ手が確保できず、区内を練ることはなかった。
26日は朝から区民らが日吉神社に集合。境内社の水無月神社に安置されているみこしの搬出に取りかかった。神社の階段はこう配が急で少ない人力での移動は難しく、クレーンでみこしを空高くつり上げ平地まで降ろした。
平地でみこしを台車に載せて、区民らが「わっしょい、わっしょい」と声を張り上げながら引っ張った。笛や太鼓の音が流れるにぎやかな雰囲気の中で、地元の小学生らも交じって汗を拭いながら目的地の水無月広場まで歩いた。
広場には祭礼のために6年ぶりに御仮屋(おかりや)が建てられており、若者らが慎重にみこしを奉納。集まった区民ら約70人で参拝した。区長の藤間さんは「クレーンでつり上げたり、台車で巡行したりと初めてのことばかり。奉納できてほっとしている」と話していた。祭りは27日も続き、御仮屋のみこしは日吉神社に戻された。
(※福井新聞社提供。無断転載を禁止します。記事に関するお問い合わせは福井新聞社へ。)