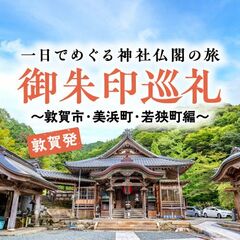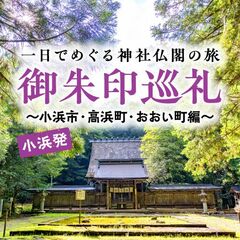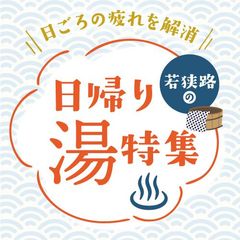昨年7月、福井県小浜市の北川水系で絶滅が懸念されていた淡水魚「ヤリタナゴ」の生息が45年ぶりに確認されたことが、福井市自然史博物館などの調査で分かった。北川水系では1979年に採集された個体の標本を最後に、生息を明確に裏付ける記録がなかった。遺伝的に外部から持ち込まれたものではなく同水系固有の個体の可能性が高く、今後の環境保全に向けた指標になるとしている。
ヤリタナゴは東北地方太平洋側を除く本州から四国、九州にかけ分布する在来種。生息環境の悪化などで環境省レッドリストで準絶滅危惧に、福井県版で地域レベルで絶滅の恐れが高い「要注目」に指定される。
昨夏に北川水系で見つかった個体は2匹で、福井市出身で京都府立海洋高(宮津市)の中野教諭が採集。同博物館の学芸員、龍谷大生物多様性科学研究センター(大津市)の博士研究員と調査、研究に当たった。
調査では▽口に長いひげがある▽背びれの膜に黒斑がある-などの特徴からヤリタナゴと判別。北川水系での発見記録を調べたところ、同博物館に79年採集の標本が収蔵されていた。80年代にも発見を報告した文献があったものの、根拠とした標本が不明で写真の掲載もなく、信頼性が検証できなかった。90年代以降の記録はなく、45年ぶりの生息確認と結論付けた。
ヤリタナゴなどタナゴ類は釣りなどの対象となるため生息地ではない別地域の河川に放流されるなどし、交雑が進んでいる。今回も外部から移入された可能性を考慮してDNAを調査。採集個体のDNAは石川県から京都府に自然分布すると考えられるグループの系統だった上、同グループ内の九頭竜川水系などの個体群と一致しなかったため、北川水系固有の可能性が高いと判断した。
中野さんは「北川水系で絶滅の懸念があったヤリタナゴが発見された。再び守るべき種として設定できることに意義がある」と説明。「河川改修などの際、環境保全への判断材料になる」とした。
中野さんらが調査結果をまとめた論文は、鹿児島大総合研究博物館が公開する魚類学の電子版学術誌に掲載された。福井市自然史博物館で6月29日まで79年に採集されたヤリタナゴの標本を展示している。
(※福井新聞社提供。無断転載を禁止します。記事に関するお問い合わせは福井新聞社へ。)