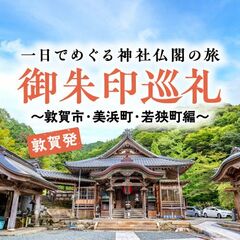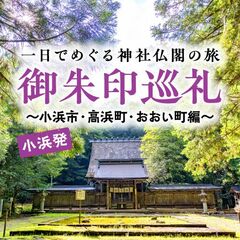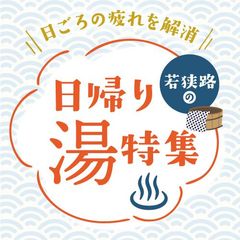本番に向け、神楽の稽古に励む新小松原区の住民ら=9日、同区の三右衛門町会館
本番に向け、神楽の稽古に励む新小松原区の住民ら=9日、同区の三右衛門町会館 大人に太鼓のたたき方を教わる小松原川西区の子どもたち=8日、同区の小松原川西会館
大人に太鼓のたたき方を教わる小松原川西区の子どもたち=8日、同区の小松原川西会館
小浜市西津地区で6年に1度、巳年(みどし)と亥年(いどし)に行われる宗像(むなかた)神社式年七年大祭(西津七年祭)が5月3~5日に営まれる。地区内では大太鼓や神楽など祭りを彩る余興の稽古が続けられ、熱気が徐々に高まっている。祭りの担い手不足といった課題にも苦慮しながら、住民は本番に向け汗を流している。
かつて漁師町として栄えた同地区の豊漁と海上安全などを祈る祭り。300年以上続くとされ、県の無形民俗文化財に指定されている。同神社のご神体を収めた神輿(みこし)や「船玉」と呼ばれる精巧な船の模型などが区内を練り歩き、住民らが大太鼓、神楽、太刀、琵琶の四つの余興を披露する。
余興は小松原川東、小松原川西、新小松原の各区が担う。このうち大太鼓を担当する小松原川西区は2月初旬に稽古を始めた。平日午後5時半から同区の会館に集まり約3時間半、みっちりと稽古。小学生以下の子どもは大人の指導を受けながら、かねの音に合わせ太鼓のリズムや体の動かし方などを繰り返し確認。中学生以上の太鼓の稽古では会館内に迫力ある音が響き渡り、棒振りを担当する男衆は勇壮な棒裁きに磨きをかけていた。
前回に続き祭りに参加する西津小6年の児童は「頑張ってたたき方を覚えて、祭りを迎えたい」と意気込む。
神楽を担当する新小松原区の4町は週2回、三右衛門町会館で太鼓、笛の稽古に励んでいる。約40年前は町内から40人ほどが祭りに参加していたが、今回は20人ほどに半減。人口減少に伴い担い手不足が懸念されたが、親が町内出身の子ども4人を町外から太鼓の担当に充て人手を確保した。
神楽の祭礼委員長は「若い人も少なくなり継承も難しくなっている」と苦悩するが「今回もみんなが集まってくれて本当にありがたい。参加する人も見物客も楽しめる祭りにしたい」と話している。
(※福井新聞社提供。無断転載を禁止します。記事に関するお問い合わせは福井新聞社へ。)