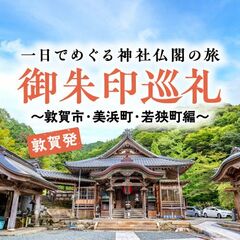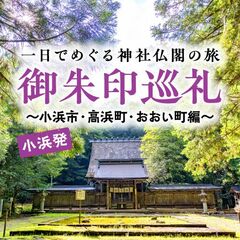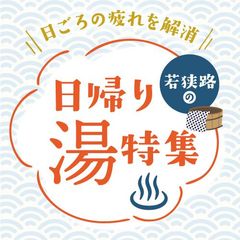桐油の採取などに使われた当時の道具などが並ぶテーマ展=小浜市遠敷2丁目の県立若狭歴史博物館
燃料用などとして栽培されていた樹木アブラギリをテーマにした福井県立若狭歴史博物館(小浜市)の「ちょっとむかしのくらし展『ころび-若狭のアブラギリ』」展が3月9日まで開かれている。種から採った工業用の油「桐油(きりゆ)」は福井県がかつて国内トップの生産量を誇り、特に若狭地域で盛んに栽培されていた。種を採取する道具など約70点を展示、当時の様子を知ることができる。
桐油はかつて明かりの燃料や、和傘、ちょうちんなどのはっ水材に用いられた。明治期からは塗料などの原料として使われ、昭和初期まで国内で盛んに生産された。福井県産の桐油は全国で60%のシェアを占め、若狭地域は江戸時代に小浜藩がアブラギリの栽培を奨励したため有数の産地だった。同地域ではアブラギリや実を「ころび」と呼んでいる。
展示ではアブラギリの種を採る作業の写真や種の殻を砕くための臼ときねや「トーシ」「チャッチコン」などと呼ばれる砕いた殻と種を分別する道具などが並ぶ。
戦後、桐油は石油化学工業の発展で需要が減り、県内では1966年に若狭町で種が集荷されたのが最後の記録となっている。展示会では文化財の修繕に用いる塗料に関する研究など、桐油の活用に向けた取り組みも紹介している。
同館の担当者は「当時の油の生産を知る人も少なくなってきている。昔の様子だけでなく、活用を目指す人もいるということを知ってほしい」と話した。
午前9時~午後5時(入館は午後4時半まで)。第2、第4月曜日は休館(祝日の場合は翌日)。常設展示料金で観覧できる。
(※福井新聞社提供。無断転載を禁止します。記事に関するお問い合わせは福井新聞社へ。)