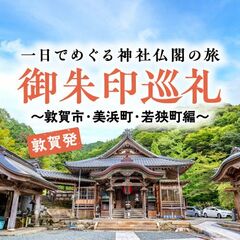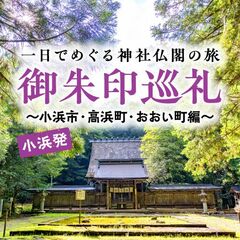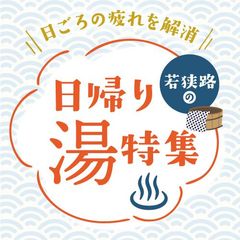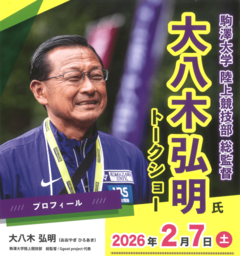優美な舞が奉納された「御船遊管絃祭」=20日、敦賀市の金ケ崎緑地
南北朝時代の船遊びを再現する福井県敦賀市の金崎宮の神事「御船遊管絃祭(おふなあそびかんげんさい)」が10月20日、同宮などで営まれた。市民らが見入る中、立烏帽子(たてえぼし)や太刀で男装した女性「白拍子(しらびょうし)」が雅楽の音色に合わせて舞を奉納した。
1336年、金ケ崎城に陣取った新田義貞が尊良(たかなが)親王と恒良(つねなが)親王を奉じて足利軍と戦った。神事は足利の兵がいったん引いた10月20日に両親王を慰めようと、敦賀湾に船を浮かべて紅葉と月をめでた故事に由来する。同管絃祭は1893年の金崎宮建立と同時に始まったとされる。戦時中に一時中断されたが、1990年に再開された。
両親王のご神体を載せたみこしが金崎宮を出発。今年は強風の影響でみこしを載せた船を海上に浮かべることができず、みこしは金ケ崎緑地に置かれた。
神事では童子役の児童がお神酒などを供え、田村典男宮司が祝詞を奏上した。白拍子の女性が優雅な舞を奉納した。
(※福井新聞社提供。無断転載を禁止します。記事に関するお問い合わせは福井新聞社へ。)