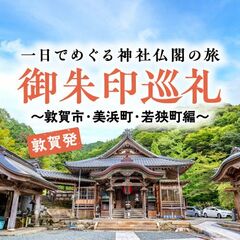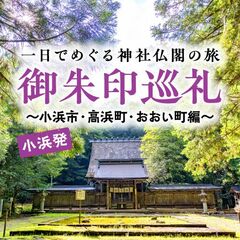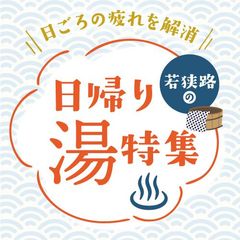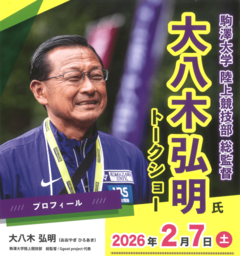製塩土器などを並べ大飯郡の成り立ちを紹介した特別展=21日、おおい町郷土史料館
製塩土器などを並べ大飯郡の成り立ちを紹介した特別展=21日、おおい町郷土史料館 遠敷郡からタイのすしを納めたと記された国宝の木簡(奈良文化財研究所提供)
遠敷郡からタイのすしを納めたと記された国宝の木簡(奈良文化財研究所提供)
若狭国に大飯郡誕生から今年1200年を迎え、福井県おおい町郷土史料館で特別展「大飯郡1200年」が開かれている。同郡の成り立ちに密接に関係したとされる製塩と律令(りつりょう)制に焦点を当て、古墳~平安時代の遺跡から出土した土器や、タイのすしを納めたことを記す奈良・平城宮跡で見つかった国宝の木簡など史料約60点を展示、解説している。11月16日まで。
若狭国はかつて遠敷郡・三方郡の二郡だった。825年に遠敷郡が分割され大飯郡が生まれたことが展示史料の歴史書「日本紀略 六」(平安時代末期)に著されている。
若狭国で古墳時代前期に土器を使った製塩が始まった。大飯郡の成り立ちには、盛んに行われた塩生産と律令制の成立が関わっているとされる。
展示では同時代の大島半島の浜禰(はまね)遺跡や平安時代の吉見浜遺跡で出土した土器を並べた。時代を追って大型化しており塩の生産が増えたと見られる。若狭国は律令制の下、塩を生産する国として位置づけられ、特産物を税として納める「調」を要請されたことが影響したと考えられるという。塩の生産増に伴い遠敷郡の人口が増えたため大飯郡が成立したとされる。
若狭国からは塩のほか魚なども納められた。平城宮跡から出土した国宝の木簡には「若狭国遠敷郡 青里御贄 多比鮓壱塥」と記され、現在の高浜町青からタイのすしが納められたことが分かる。
郡の官人が政務を行う役所「郡衙(ぐんが)」は三方郡では城縄手遺跡(若狭町)、遠敷郡は小浜市の遠敷か松永地区のいずれかに位置したとされる。大飯郡の郡衙の場所について学芸員は「大型製塩炉が近くにあったなどさまざまな理由で、小堀遺跡はじめ四カ所の遺跡のどこかではないか」と推察する。
国宝の展示は26日~11月1日。入館料300円。午前9時~午後6時。期間中の休館日は10月27日、11月4、10、11日。
(※福井新聞社提供。無断転載を禁止します。記事に関するお問い合わせは福井新聞社へ。)