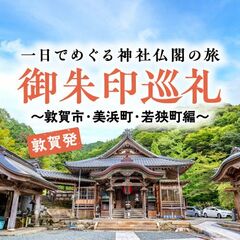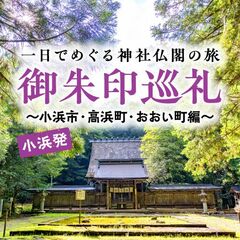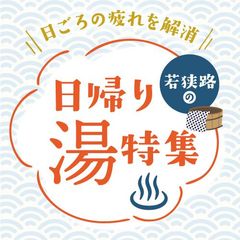リニューアル1周年記念企画展で展示されている山車の水引幕=敦賀市みなとつるが山車会館
福井県敦賀の秋の風物詩「敦賀まつり」で巡行される山車(やま)を構成する部材や装飾品を展示する企画展「つるがの山車は“やま”なんです」が、同市みなとつるが山車会館で開かれている。1月30日までの第1期では、山車の舞台座を飾る水引幕などが並び、縁起の良い花鳥図の刺繍(ししゅう)が、おめでたい雰囲気を醸し出している。
山車会館のリニューアル1周年を記念した企画展で、1階のウエルカム・ギャラリーに展示している。
まつりで巡行される6基の山車のうちの一つ「鵜飼ケ辻子(うかいがずし)山車」の水引幕2枚を展示。1枚は江戸時代後期から明治時代にかけて制作されたもので、長寿を象徴する松、子孫繁栄を意味する親子の鶴がモチーフとなっている。明治時代に作られたもう1枚は、平安や繁栄を象徴する桐(きり)と鳳凰の図柄の刺繍が施されている。
東町山車の舞台座の四隅に差し込む「錺(かざり)金具」は、銀色の竹の枝に金色のスズメが止まっている金工品で、羽毛まで丁寧に彫られ、生き生きとした様子が表現されている。東町は旧敦賀町内でも裕福な商家が住む町として知られ、山車を飾る懸装(けそう)品も豪華なものが残されているという。
山車会館の学芸員は「普段は動いている山車全体に目が行き、細部にまで注目することは少ないと思うが、今後、新たな視点で山車巡行やまつりを楽しんでもらえれば。また、山車の保存会の皆さんが毎年、情熱を注いで飾りつけをしていることも知ってほしい」と話していた。
企画展は3期に分かれ、2月1~27日の第2期では山車の車輪や欄干など、3月1~28日の第3期では舞台座の上に載せられる武者人形の骨組みや衣装、甲冑(かっちゅう)を展示する。入館料300円。
(※福井新聞社提供。無断転載を禁止します。記事に関するお問い合わせは福井新聞社へ。)