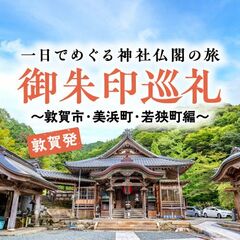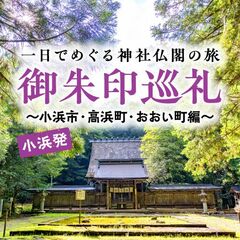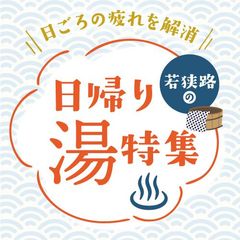旧ソ連のスターリン体制下でシベリアに強制追放されたリトアニア人の苦難の歴史を紹介する企画展「シベリアからの生還 リトアニア人たちの流浪物語」が福井県敦賀市の資料館「人道の港敦賀ムゼウム」で開かれている。リトアニア国立博物館が所蔵する追放者の写真や生活用品など約80点の資料を展示。大戦中に外交官杉原千畝が「命のビザ」を発給した地として知られるリトアニアと敦賀はゆかりが深く、同博物館との共催で実現した。
バルト3国のリトアニアは第2次世界大戦中の1940年にソ連に併合され、41~44年のナチス・ドイツによる占領を経て、再びソ連の支配下に入った。「人民の敵」とみなされた多くのリトアニア人が弾圧を受け、53年までに約28万人がシベリアや北極圏などに移送された。うち7割が女性と子供だったという。追放者の3分の1は帰還できなかった。
強制移送された人々は、安価な労働力として過酷な仕事を割り当てられた。企画展では、いてつくような冷たい水の中で漁の網を引いたり、ダムの建設現場で働いたりする様子を収めた写真パネルが展示されている。また、白樺(しらかば)の木を何層も重ねて手作りした水筒や車のタイヤで作った靴などの生活用品も並び、過酷な状況下でも尊厳を失うことなく、工夫して生き抜いた跡がうかがえる。
会場内では、駐日リトアニア大使館のオーレリウス・ジーカス特命全権大使によるメッセージ動画が流され、「杉原千畝氏の命のビザにより救われたユダヤ人がたどり着いた敦賀はリトアニアにとっても重要な所です。展示を通じて、つらい過去を思い出すことで、世の中が少しでも平和に近づくことを祈念します」と日本語で話している。
敦賀とリトアニアの子どもたちで完成させた、横6メートル、縦2・2メートルの巨大な橋の絵も展示している。
今年は戦後80年の節目に当たる。ムゼウムの担当者は「あの時代、多くの人々の苦しみの根源に戦争があったこと、戦争は二度と繰り返してはいけないことを再認識してもらいたい」と話していた。企画展は6月15日まで。水曜休館。
(※福井新聞社提供。無断転載を禁止します。記事に関するお問い合わせは福井新聞社へ。)