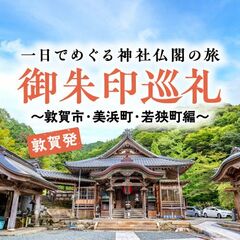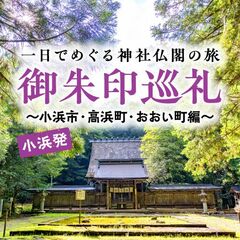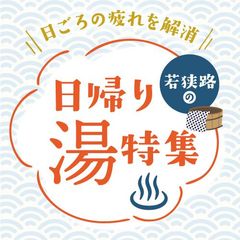1990年代の年縞コアの手書き記録や層のスケッチなどの資料が並ぶ企画展=14日、若狭町鳥浜の県年縞博物館
三方五湖での湖底堆積物「年縞(ねんこう)」調査の歴史を紹介する企画展が5月6日まで、県年縞博物館(若狭町鳥浜)で開かれている。三方湖で発見された日本初の年縞や、現在、世界標準の「年代のものさし」となっている水月湖年縞の1990年代の掘削などを当時の資料で紹介している。
年縞は1年に1枚ずつ堆積する特殊な地層で、水月湖には7万年分で45メートルある。含まれる花粉や元素組成を調べることで当時の気候が分かる。企画展は、2014年以来5回目の水月湖での掘削調査が6月から行われることを記念し、年縞博が開いた。
三方五湖では1991年に本格的なボーリング調査が三方湖で行われ、日本で初めて年縞が発見された。展示では、年縞のあった深さ27・49~28・49メートルの部分スケッチを紹介。当時はデジタルカメラやパソコンが普及しておらず、手書きで鉛筆の濃淡や線の太さを変えて層を詳細に記録している。
三方湖での年縞発見をきっかけに、同年に始まった水月湖年縞の調査資料も展示。水月湖年縞が7万年分45メートル連続していることが初めて確認された93年の年縞コアの記録には、「火山灰」「軽石質」など堆積物の性質や採取範囲が手書きで記されている。
年縞博の学芸員は「当時、いろいろな不便があった中で調査を進めていった研究者たちの情熱が感じられると思う。展示を通して、6月からの掘削に多くの人に関心を持ってもらえたら」と話している。火曜休館。入館料は一般500円、小中高生200円。
(※福井新聞社提供。無断転載を禁止します。記事に関するお問い合わせは福井新聞社へ。)