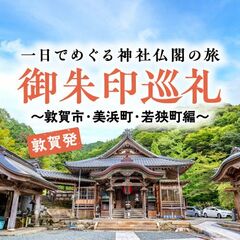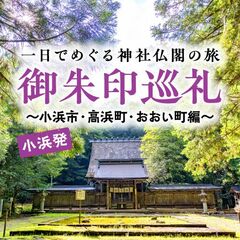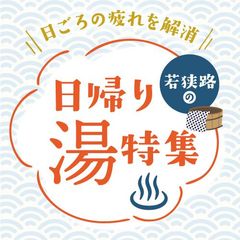大谷吉継が発給した文書や屏風を紹介する企画展=16日、敦賀市立博物館
大谷吉継が発給した文書や屏風を紹介する企画展=16日、敦賀市立博物館 豊臣秀吉の弟秀長の家臣に宛てた吉継の書状。今回初めて公開された
豊臣秀吉の弟秀長の家臣に宛てた吉継の書状。今回初めて公開された
敦賀城主を務めた戦国武将、大谷吉継の生誕460年を記念した企画展「拝啓、四百六十の君へ」が7月16日、福井県敦賀市立博物館で始まった。豊臣秀吉の弟秀長の家臣に宛てた吉継の書状は昨年発見された新出史料で初公開。このほか、敦賀城主になりたての時期に発給した重要文化財の文書など43点の史料を並べ、義を重んじた武将として人気の高い吉継の実像に迫っている。8月24日まで。
秀長の家臣池田秀雄に宛てた書状は天正17(1589)年ごろ、秀長が居城とした大和郡山城(奈良県)の普請に際し、堺の代官だった吉継が労をねぎらう内容。秀長は来年のNHK大河ドラマの主人公で、敦賀市立博物館学芸員の北村太智さん(27)は「吉継と秀長のつながりがうかがい知れる史料。本邦初公開で企画展の目玉」と話す。
幕末から明治にかけて活躍した絵師菊池容斎が描いた「関ケ原合戦図屏風(びょうぶ)」は、敦賀市立博物館の所蔵品の中でも一、二を争う人気を誇る史料で、病のため顔を頭巾で覆った姿で手にやりを握る大谷吉継が描かれている。横約2・3メートルの右隻と左隻の二つから成り、迫力たっぷりに来場者を迎える。
豊臣政権の有力大名だった上杉景勝の重臣直江兼続に吉継が送った文禄3(1594)年の黒印状は、草津での湯治で体調が回復したことを知らせる内容。目の状態が悪くて、花押(サイン)を書くべきところ黒印で済ませてしまった非礼をわびる文面で、吉継の心遣いが見て取れるという。
ほかにも、吉継の家臣への気遣いが読み取れる書状が展示され、学芸員の北村さんは「武力で威嚇したり、圧力で従わせたりするタイプでなく、『アメとムチ』をうまく使いこなし、良好な人間関係を築きながら統治していたことがうかがえる。展示を通して吉継の人となりに触れてもらいたい」と話している。
入館料300円(高校生以下無料)。8月10日午後1時半から、関連イベント「大谷吉継サミット」が敦賀市民文化センターで開かれ、研究報告やパネル討論を通して、大谷吉継の事績を紹介する。
(※福井新聞社提供。無断転載を禁止します。記事に関するお問い合わせは福井新聞社へ。)