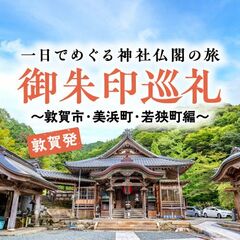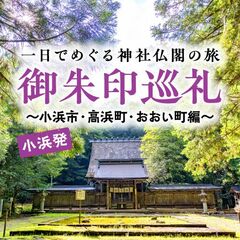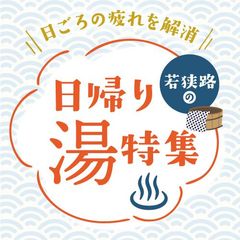山に囲まれた福井県若狭町の鳥羽谷に点在する文化財の歴史や伝統行事を後世に残そうと、同町無悪の元教諭、高橋さんが「鳥羽谷の石の文化財」と「鳥羽谷の四季折々 民俗・年中行事」の二つの冊子を発刊した。墓地や峠道にポツンと立つ石造物や各地域で受け継がれる伝統行事を隅々まで調査し、手書きの文書と写真で紹介している。
高橋さんは、1961年から旧三方、上中両町の小中学校で38年間教諭として働き、社会科を教えていた。退職後の2000年に無悪の歴史文化をまとめた冊子を発行。現在は、無悪など13集落がある鳥羽谷の冊子を年間2冊のペースで制作している。鳥羽谷は南北約6キロの細長い盆地で、今回も文献調査のほか、現地に足を運び住民に聞き取りし、それぞれ2カ月ほどかけてまとめた。
石の文化財の冊子では、鳥羽谷にある宝篋(ほうきょう)印塔、五輪塔といった石造の塔や地蔵などを紹介。宝篋印塔は、麻生野や無悪、大鳥羽など5区で現存することを確認し、造立が始まったとされる鎌倉時代から時代が移るにつれ、飾りが派手になっていることを写真とともに説明している。
地蔵は、平地から峠まで17カ所にあるのを見つけて紹介。多くの地蔵は峠にあり、理由として鳥羽谷は山で囲まれ早くから峠道が発展したと考察した。「残された石造物には先祖たちの暮らしを探る手がかりがある」と強調している。
民俗・年中行事の冊子では、神社の拝殿に集まった子どもが「ヤーレチョボ、ちょっときて、銭まけ、もっとまけ」と歌い、周囲の大人が拝殿の天井めがけて放り投げた硬貨を子どもが懸命にかき集める大鳥羽の奇習「ヤレチョボ」を紹介。かつては養蚕が盛んな集落で、繭の形をした餅をまく風習があったが、いつしか小銭に変わった経緯や、県外にも似た奇習があると記した。
虫送りの要素を併せ持つとされる海士坂の「送り盆(人形もやし)」(県指定無形民俗文化財)、地域に根付いた年中行事なども解説している。
高橋さんは「先祖が大切に守って今に残っている。当時の宗教心や生活にも思いをはせてほしい」と話している。冊子は、B5判で町立図書館と小浜市の県立若狭図書学習センターで借りられる。問い合わせは高橋さん=電話0770(64)1645。
(※福井新聞社提供。無断転載を禁止します。記事に関するお問い合わせは福井新聞社へ。)