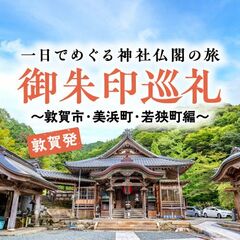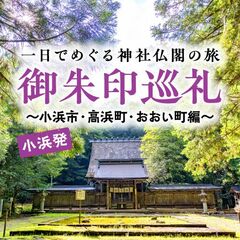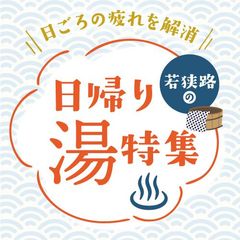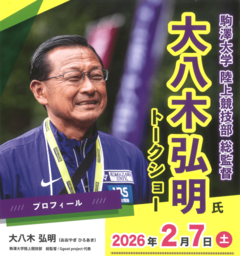全国のお城の形に焦点を当てた企画展「城コレ2025・秋~城の形(イメージ)~」が12月26日まで、福井県美浜町若狭国吉城歴史資料館で開かれている。大野館長が旅先で集めた城のフィギュアや、城の形をしたお菓子の箱など、175点を展示。年代で異なる城造りの方法やデザインを楽しめる。
城巡りが趣味の大野館長は2015年から毎年、私費で買い集めた土産品を「城コレ」と題して展示している。
城造りでは、下層部を建築した後に物見台など「望楼」部分を載せる「望楼型」や、下層部と上層部を一体的に組み上げる「層塔型」があることをパネルで説明。望楼型は織田信長が築いた安土城(滋賀県)、層塔型は江戸城などがあるという。大野館長は「天守の高層化や耐震のため、年代が進むにつれて層塔型が天守の一般的な形になった」と解説し、展示品からもそれぞれの城がどちらの型に当たるか見て取れる。
時代によって形を変えた大阪城はフィギュアで変遷を紹介。豊臣秀吉が築城し、1615年の大坂夏の陣で焼失した城や、その後に徳川幕府が焼け跡を埋めて築城し落雷により焼失した城、徳川幕府が造った石垣の上に豊臣時代の天守をモデルに昭和初期に再建された城を並べた。現在の大阪城が豊臣と徳川両方の要素を融合したハイブリッド城であることを伝えている。
鶴ケ城(福島県)は、屋根の瓦の色が黒と赤で異なるフィギュアとお菓子の箱を展示。大野館長は「2000年代に入ってからの発掘調査などで幕末当時は釉薬(ゆうやく)を使った赤い瓦が屋根に使われていたことが判明し、黒い瓦から赤い瓦にふき替えられた。展示品は吹き替え前後に購入したもの」と説明。「それぞれの城の形の特徴とともに、同じ城のデザインの違いも見つけて楽しんでほしい」と来館を呼びかけている。
入館料一般100円、中学生以下50円。月曜休館、祝日の場合は翌日休館。
(※福井新聞社提供。無断転載を禁止します。記事に関するお問い合わせは福井新聞社へ。)