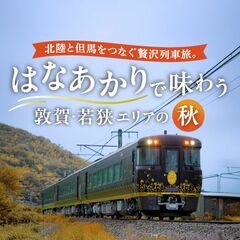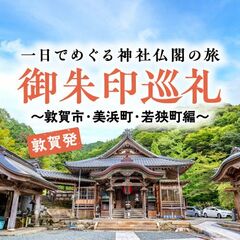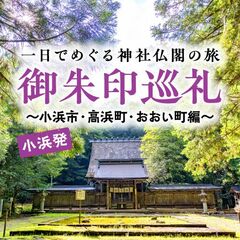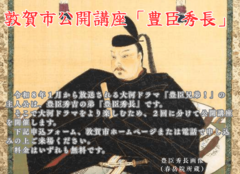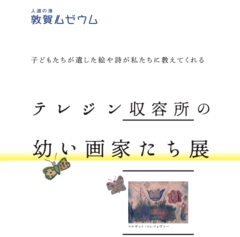福井県おおい町本郷小3年生35人が11月26日、地元の若州一滴文庫の「くるま椅子劇場」で竹人形文楽の公演を行う。児童は同町出身の直木賞作家、故水上勉さんが旗揚げした人形劇団「若州人形座」の座長から人形の操り方を学び、本番に向け稽古に励んでいる。同校は2007年にも手ほどきを受け上演しており、今回は18年ぶりの“復活公演”となる。午前10時15分から。一般の観覧もできる。
水上さんは一滴文庫を設立した翌1986年、人形劇団を立ち上げ水上さんの指導を受けた本郷小児童が文楽を披露したという。88年には敷地内に同劇場を開設した。
2006、07年には同人形劇団の静永座長の指導を受けた同校児童が公演した。今年7月、校外学習で同文庫を訪れたのを機に上演に挑戦することになった。
上演作は水上さんが人形劇のために書いた脚本「一滴の水」。同町大島出身で臨済宗の老師・儀山善来(ぎさんぜんらい)(1802~78年)の「一滴の水さえ粗末にするな」という教えを基にした作品で、同文庫の名前の由来にもなっている。
講師は今回も静永さんが務め、児童は語り手と人形遣いに分かれて9月上旬から週1回、練習に励んでいる。
背丈1メートルほどの竹人形の顔や手、足を児童3、4人で分担、息を合わせて操る。語りに合わせ縄を縛るような複雑な動作もあり、児童は四苦八苦していた。身ぶり手ぶりで動かし方を教わりながら表現を磨き、セリフに合わせることも意識していた。
人形の腕を担当する児童は「声に合わせて動かすのは難しいけれど、みんなで協力して公演を成功させたい」ときっぱり。静永さんは「自分なりの表現方法を考えながら体験してほしい。児童の思い出に残るとうれしいし、人形遣いになりたいという思いにつながれば」と話した。
(※福井新聞社提供。無断転載を禁止します。記事に関するお問い合わせは福井新聞社へ。)